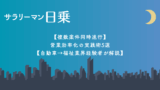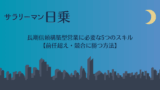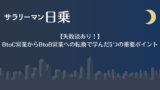「AIでブログ記事が簡単に作れる」という話をよく聞きますが、実際のところはどうなのでしょうか?
ChatGPTを使えば確かに短時間で記事を作ることは可能ですが、使い方を間違えると法的リスクがあったり、期待した品質にならなかったりすることも。
この記事では、実際にChatGPTを使ってブログ記事を作成している筆者の体験談を交えながら、法律面の注意点からステップ別の活用法まで、現実的で実践的な情報をお伝えします。
まず知っておくべき法律面の基礎知識

著作権について
ChatGPTで作成したコンテンツの著作権について、多くの人が不安に思っているのではないでしょうか。
OpenAIやGoogleの公式見解をまとめました。
OpenAIの公式見解
OpenAIの公式見解によると、「規約などを遵守する限り、ChatGPTで製作された出力内容について、利用者はあらゆる目的(販売や出版などを含む商業利用も含む)において利用可能」とされています。
Googleの公式見解
さらに重要なのは、Googleの見解です。Googleは2023年2月にAI生成コンテンツに関する公式ガイダンスを発表し、以下のように明言しています:
AI生成コンテンツそのものはペナルティ対象ではない:「AI生成コンテンツという理由だけで、Googleからペナルティを受けることはありません」
品質に重点を置く:「コンテンツがどのように制作されたかではなく、その品質に重点を置く」
ユーザーのための価値提供が重要:「ユーザーの役に立つコンテンツを第一に考え検索エンジンに好かれようとするコンテンツを避けるように」
つまり、基本的にはChatGPTが生成した文章を商用利用・SEO目的で使用しても問題ありません。
注意すべき法的ポイント
ただし、以下の点には十分注意が必要です:
1. 他人の著作物を参考にした生成は危険
他人の著作権のある記事やコンテンツ、画像・映像などのURLを入力し、生成物を自作コンテンツとして公開することは著作権侵害となり得ます。
2. 生成内容の責任は利用者にある
ChatGPT生成物の業務利用の際にも自社の責任の範囲内でチェックを行うことが求められます。
3. SEO操作目的での大量生成は危険
Googleは「検索結果のランキング操作を主な目的として、コンテンツ生成に自動化(AI を含む)を利用することは、スパムに関するポリシーに違反します」と明言しています。つまり、SEO操作だけを目的とした低品質なAI生成コンテンツの大量投稿はペナルティ対象です。
ステップ別ChatGPT活用法
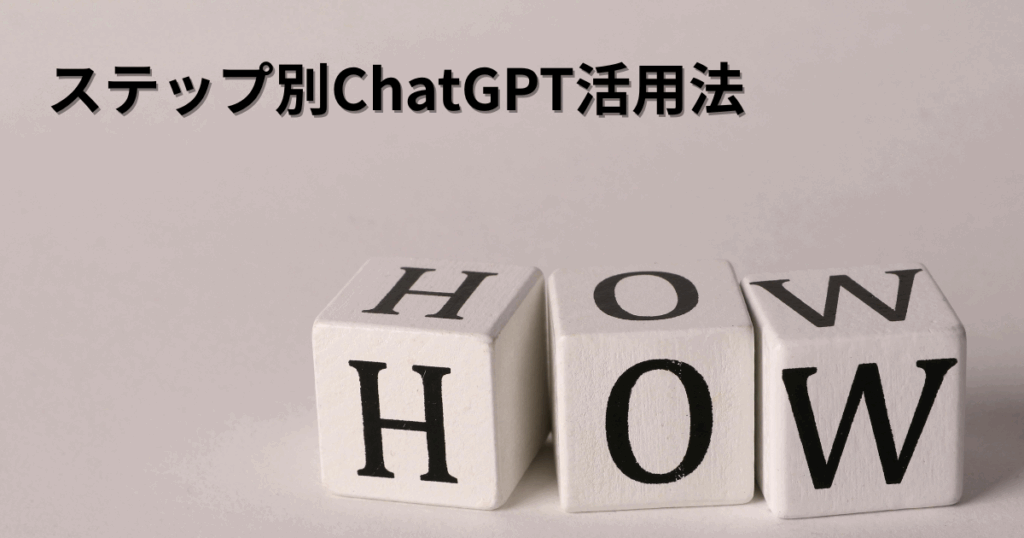
ステップ1:キーワード選定・構成案作成
ChatGPTが最も得意とする分野の一つが、記事の構成案作成です。
実体験での感想
実際に使ってみると、記事構成やキーワード選定の精度は非常に高いと感じます。自分では思いつかなかったアングルや見出しを提案してくれることも多く、発想の幅が広がります。
効果的なプロンプト例
以下の条件でブログ記事の構成案を作成してください:
・メインキーワード:「副業 始め方」
・ターゲット:20代〜30代のサラリーマン
・検索ニーズ:副業を始めたいが何から手をつければいいかわからない
・記事の方向性:初心者向けの具体的な手順を紹介
ステップ2:見出し・本文作成
構成案ができたら、各見出しの本文を作成していきます。
実体験での感想
文章出力については「すごいなー」と感じることが多いです。特に導入文や説明文など、自分だけで書くと時間がかかる部分を効率化できます。一緒に記事を作りながら、自分の文章力の成長も早められると感じています。
注意点
構成案すべてをまとめて生成しようとすると、大見出しごとの文章量が少なくなってしまいます。見出しごとに分けて生成することをおすすめします。
ステップ3:誤字脱字チェック・校正
実体験での感想
誤字脱字のチェックは本当に便利です。人間が見落としがちな細かいミスも発見してくれるので、最終チェックの時間が大幅に短縮されます。
効果的なプロンプト例
以下の文章の誤字脱字をチェックし、修正案を提示してください。
また、より読みやすくするための文章改善提案もお願いします。
[チェックしたい文章を貼り付け]
ステップ4:人間の視点で仕上げ
最も重要なポイント
「自身の体験を追加」は人間にしか行えない工程であり、ブログ記事のSEO評価を高めるうえでも非常に重要です。
実際に使ってみたリアルな感想

メリット
実際にChatGPTを使ってブログ記事を作成してみて感じたメリットは以下の通りです:
構成作成とSEO対策の向上
記事構成やキーワード選定の提案が的確で、これまで自分がしっかり練れていなかったSEO対策の部分がよりクリアになりました。正直、記事としては良くても SEO面が甘かった部分があり、ChatGPTと一緒にすり合わせを行っていくことで、記事のクオリティがアップしたと実感しています。
誤字脱字チェックが便利
人間が見落とすミスも発見してくれるため、最終チェックの時間が大幅に短縮されます。
文章の質と表現の幅が向上
文章出力については「すごいなー」と感じる場面が多く、特に自分の頭だけで考えてもできないような文章のトーンや表現について、いろんな提案があるため、気づきになりました。
成長サイクルの加速
本来自分で試行錯誤を重ねて勉強していくSEOやデザイン、コーディングの知識、文章力、構成を作る力などは、ChatGPTと壁打ちをしたり、アドバイスをもらってやっていくことで、①スピード②クオリティともにUPしました。そうすることで成長サイクルが短くなって、加速度的に成長できていると感じています。
一緒に記事を作りながら、自分のライティングスキルも向上させられるのが最大のメリットです。
注意点・課題
一方で、実際に使ってみて感じた課題もあります:
情報の抜粋・まとめが苦手
多くの情報から抜粋してまとめるような作業は苦手な印象です。複数のソースから正確な情報を統合する際は、人間による確認が必須です。
間違いがまだ多い現実
ChatGPTが間違いや嘘を回答することは「ハルシネーション」と呼ばれる現象で、GPT-5で改善されたかもしれませんが、まだ完璧ではありません。
実際に体験した例として、ある特定のイベントについて調べてもらった際、必要な概要が足りなかったり、そもそも間違っていたりということがありました。ChatGPTの無料版ではURL参照ができないためか、架空のイベント情報を「めちゃくちゃ生成しちゃった」こともあります。
特に以下のような情報は要注意です:
自身が運営している地域メディアでの判断
筆者が自身で運営している地域メディアの記事作成でChatGPTをほぼ利用しなかったのは、「間違った情報は載せてはいけないし、自身の獲得した情報でないと信用ができない」からです。情報ソースが一次的なものか二次的なものかのチェックが重要ですが、出典を出してもらっても扱いきれないし、まだ扱いにくいのが現状です。
そのため、リザルトチェックはしっかり自分で行い、基本的な情報の獲得は人間が行ったほうが安全です。もちろん、全く知らない物事の概要を知ることには重宝しますが、記事にそのまま転用するのは危険だと感じています。
生成結果が不安定
ChatGPTにログインし直したり、日を改めたりすると、生成結果のニュアンスが変わってしまうことがあります。
初心者におすすめの実践的活用法
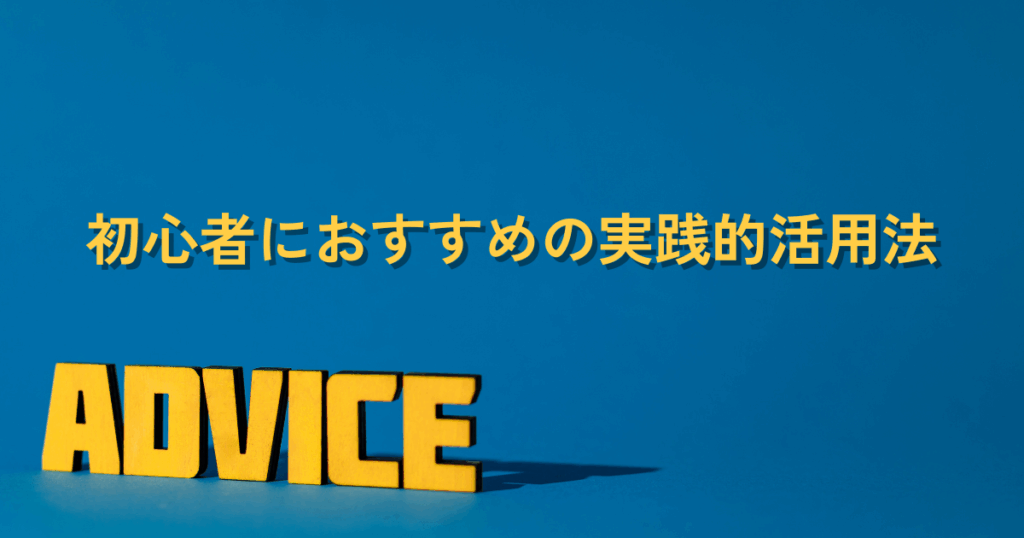
使うべき場面
以下のような場面では、ChatGPTが強力なサポートツールになります:
避けた方がいい場面
一方、以下のような場面では人間による作業を推奨します:
重要な判断基準
記事にそのまま転用するには危険だと感じる場面では、ChatGPTで概要を掴んだ後、必ず人間が一次情報を調べ直すことをおすすめします。リザルトチェックはしっかり自分で行い、基本的な情報の獲得は人間が行ったほうが安全です。
現実的な活用スタンス
完璧を求めず、あくまで「優秀なアシスタント」として活用するのがコツです。
- ChatGPTで叩き台を作成
- 人間が事実確認・修正
- 個人の体験談を追加
- 最終チェック
この流れを基本として、法律面の注意点を守りながら活用していけば、効率的で質の高い記事作成が可能になります。
まとめ

ChatGPTは確かにブログ記事作成において強力なツールですが、万能ではありません。
得意な部分(構成作成、誤字脱字チェック、文章の叩き台作成)と苦手な部分(情報の統合、事実確認、最新情報)を理解して使い分けることが重要です。
法律面の基礎知識を押さえ、現実的な期待値で活用すれば、「一緒に記事を作りながら、自分の成長を早められる」優秀なパートナーになってくれるでしょう。
まずは簡単な記事から始めて、徐々にコツを掴んでいくことをおすすめします。