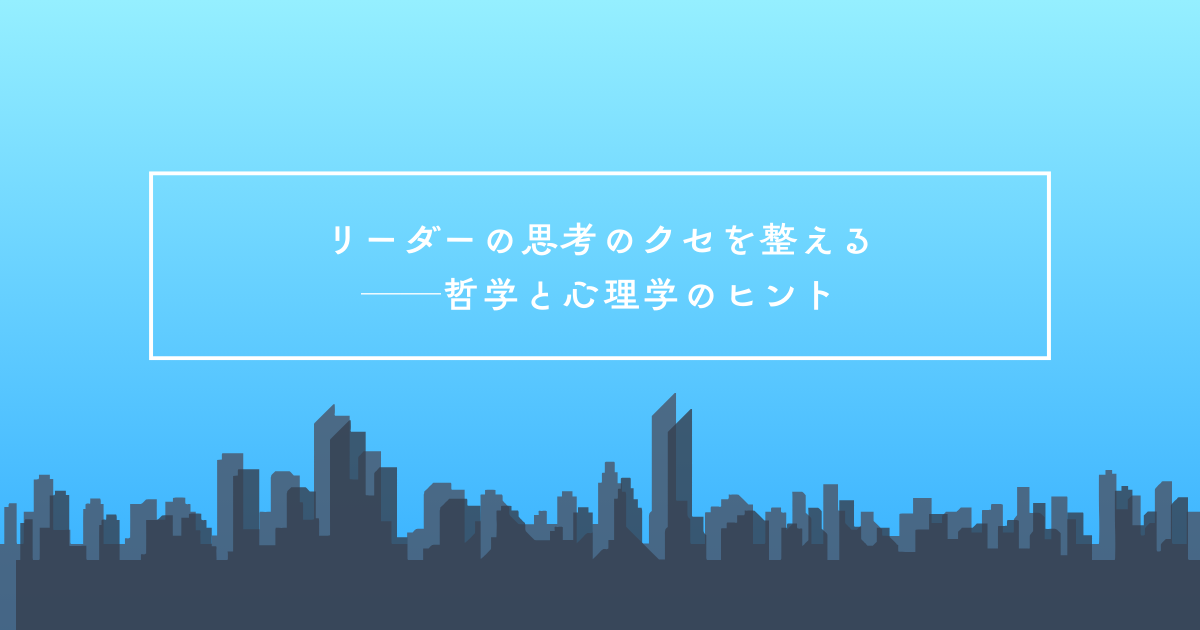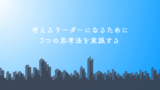リーダーになると、多くの人はまず「部下をどう動かすか」「チームをどう導くか」を考えます。
私自身もリーダー見習いとして活動していた頃、そんなことばかり考えていました。
しかし実際に直面するのはもっと身近でやっかいな課題──自分自身の思考のクセです。
「部下が思った通りに動かない」「責任は全部自分にある」「なんでもコントロールできるはずだ」……。
こうした思い込みが意思決定を歪め、コミュニケーションをぎこちなくします。
幸い、昔から人間の思考に頭を悩ませた人たちがいます。それが哲学者や心理学者です。
今回は、リーダーとして活動しながら、彼らの知恵を借りて思考のクセを整える方法を一緒に勉強していきましょう。
思考法についての記事も書いています。
興味のある方は是非ご覧ください。
よくあるリーダーの思考グセ
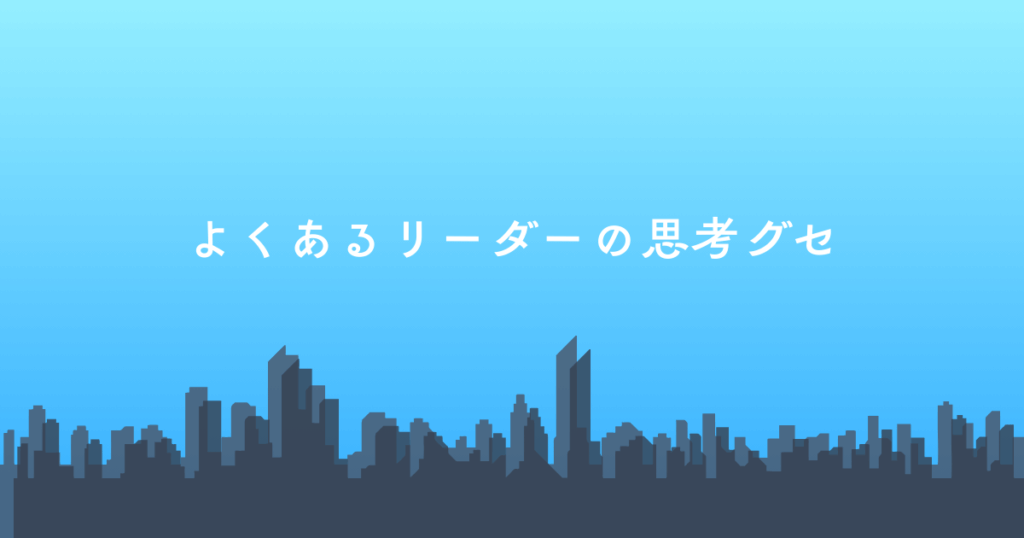
1. 部下は自分と同じように動くはずだ
私も営業チームのリーダーになったばかりの頃、
「営業ならやるかやらないか。やれて当たり前だ」と思っていました。
それまでどの会社でも最年少で、数字を自分で追う“個人プレー”が中心。
だから、後輩や部下を動かすという発想がほとんどなかったんです。
ところが、いざチーム全体の数値を管理する立場になったとき、
「なぜやらないんだ」と責めるほどに結果は遠ざかっていきました。
その時、自分の“すべき思考”がいかに強く、他人にそれを押し付けていたかに気づきました。
リーダーとしての第一歩は、自分の思考グセに気づくことだったのかもしれません。
2. すべての責任を背負い込まなければならない
責任感は大切ですが、「全部自分で抱える」という思考は、かえってチームの成長を妨げます。
リーダーは万能のヒーローではなく、仕組みを作る人です。
3. なんでもコントロールできるはずだ
会議の進行、部下の感情、成果の出方。すべてを管理できると思い込むと、現実とのギャップに苦しみます。
実際には「自分にコントロールできること」と「できないこと」が混ざっています。
私はこれが一番理解できませんでした。自分の中で「コントロールされることは当たり前」という認識が深く根付いていたからです。
哲学・心理学に学ぶリーダーの思考法
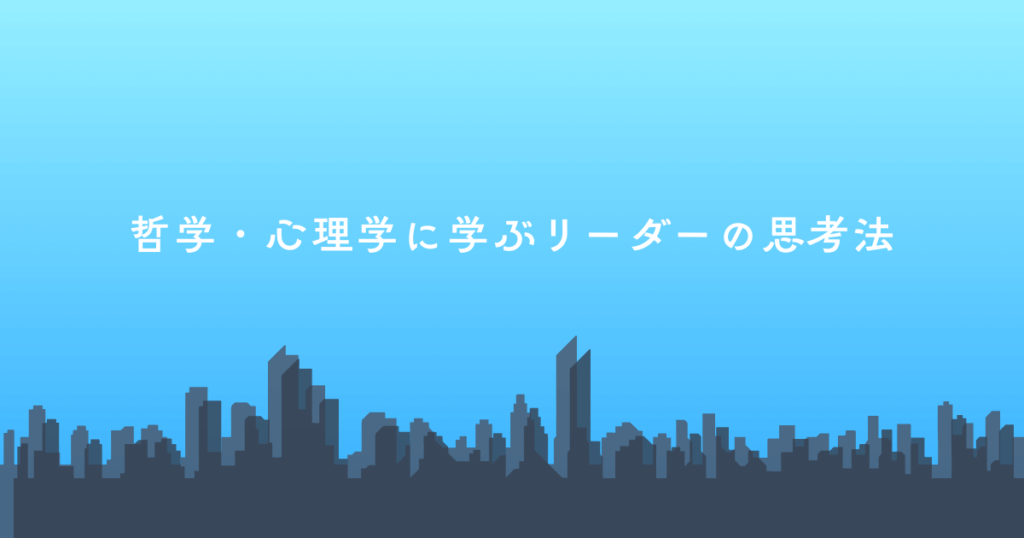
ニーチェ:「なぜ自分はそう考えるのか?」を問い直す
- 経歴:フリードリヒ・ニーチェ(1844-1900)、ドイツの哲学者・古典文献学者
- 代表作:『ツァラトゥストラはかく語りき』『善悪の彼岸』『道徳の系譜』
- 解説:思い込みに支配されやすい人間の思考を見直すことが大切。
- リーダーへのヒント:会議前に自分の意見を立ち止まって問い直すことで、偏った判断や苛立ちを減らせる。
私は特にニーチェの思想に強く影響を受けました。
『ツァラトゥストラ』をきっかけに「ルサンチマン(恨みの連鎖)」や「永劫回帰」「超人思想」などを学び、
物事を“分けて考える”感覚が少しずつ身についてきました。
それまでは、結果も人の感情も「全部自分の責任だ」と一括りにして苦しんでいましたが、
今では「コントロールできる部分」と「できない部分」を分けて捉えようとしています。
完璧ではありませんが、視点を変えるだけで気持ちが少し楽になりました。
ストア派:「コントロールできることとできないことを分ける」
- 経歴:マルクス・アウレリウス(121-180)、ローマ皇帝・哲学者
- 代表作:『自省録』
- 解説:全てを管理しようとする思考を整理。コントロールできることだけに集中する。
- リーダーへのヒント:タスクを「自分で管理できること/任せること」に分けると、チームの自主性が育つ。
私は、なかなかこれができないで困っているんですが、折に触れて何かあった時には、ノートにこのことを意識して物事の仕分けをするようにしています。
マズロー:「欲求段階でチームを見る」
- 経歴:アブラハム・マズロー(1908-1970)、アメリカの心理学者
- 代表作:『人間性の心理学』『動機づけと人格』
- 解説:部下が動かないのはやる気ではなく、欲求が満たされていない場合がある。
- リーダーへのヒント:1on1で悩みや目標を聞くなど、心理的安全や環境整備を意識する。
自身も含めて、全員が違った段階にある。それを意識するだけで心がグッと楽になりますよ。
認知行動療法(CBT):「思考のクセを検証する」
- 経歴:アーロン・ベック(1921-2021)、アメリカの精神科医
- 代表作:『認知療法と感情障害』
- 解説:「全部自分で抱えなきゃ」という思い込みを客観視し、事実と推測を分けて検証する手法。
- リーダーへのヒント:思考を整理することで、感情的な判断を避け、冷静で合理的な対応ができる。
言いすぎちゃったな、そんな時は振り返りの絶好のタイミングです。
そんな時にこそ、自身の思考のクセを知って、成長する良い機会になるでしょう。
具体的な行動に落とす

私は、下記のようなことを実践しています。
皆さんも、気に入ったことをひとつだけでもいいのいいので、やってみてくださいね。
- 会議前に自分の思考をメモに書き出して問い直す
- タスクを「自分で管理できること/任せること」に分ける
- 部下の欲求や心理状況を意識して環境を整える
- 思い込みを箇条書きで整理し、事実と推測を分けて検証する
まとめ:リーダーとしての思考整理の3ステップ
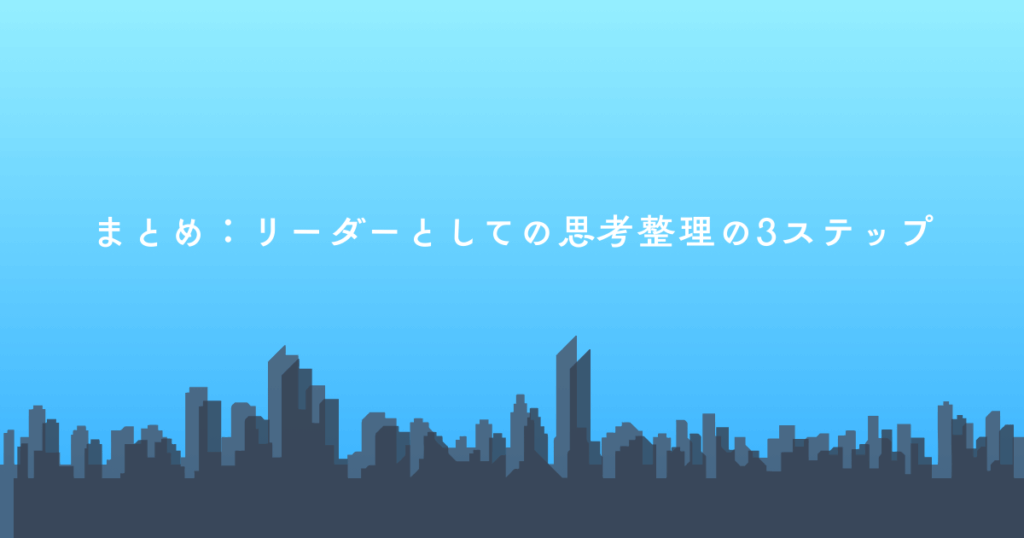
- 自分の思考を問い直す(ニーチェ)
- コントロールできることとできないことを区別する(ストア派)
- 部下の欲求や思考を理解して環境を整える(マズロー・CBT)
リーダーとしてつい「部下をどう動かすか」に目がいきますが、まずは自分の思考のクセを整えることが最初の鍵です。
小さな行動から始めるだけで、判断やコミュニケーションの質がぐっと変わります。
哲学や心理学の知恵を借りて、自分とチームの関係を整えましょう。
私自身もチーム全体の数字を自分の数字として背負う日々は、正直まだ苦しいです。
でも、部下を“動かす”よりも、“理解しようとする”方向に意識が変わりました。
人は思うように動かせない——その事実を受け入れられただけでも、大きな一歩だと感じています。