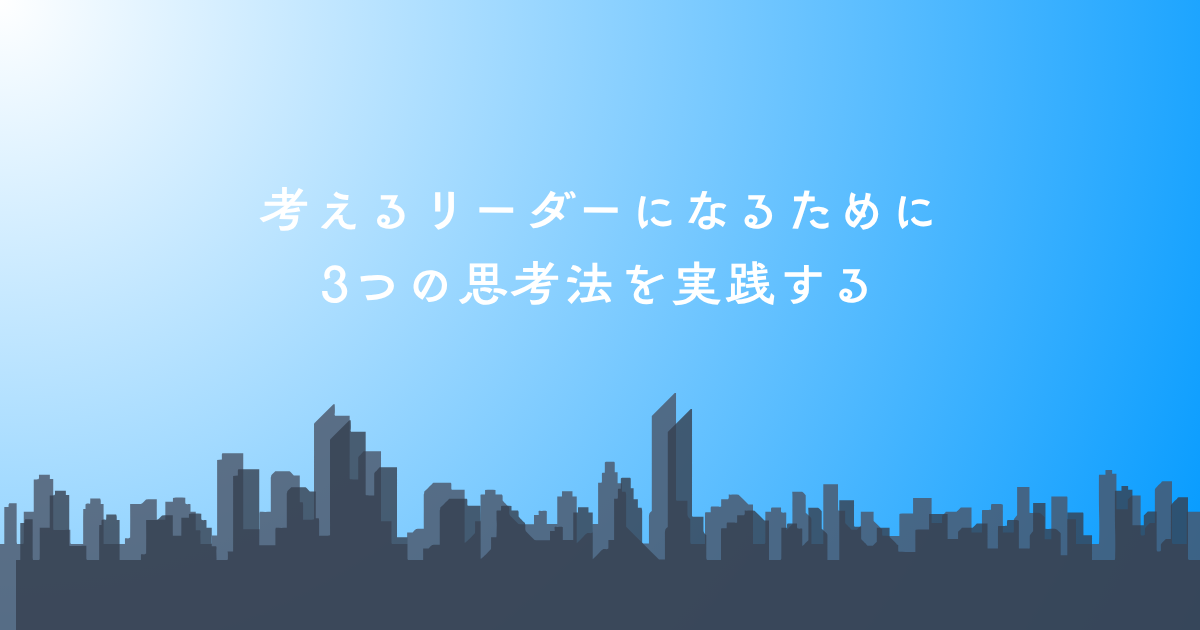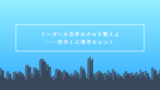今回の記事では、リーダー見習いの私が、現在職場で訓練している思考法についてご紹介します。
ロジカルシンキング、クリティカルシンキング、ラテラルシンキング。
この三つの手法を学ぶことで、これまで思い悩んでいた課題分析や打ち手の設定などに真っ直ぐ到達できるようになりました。
今回はこの三つの思考法を一緒に学んでいきましょう。
リーダー見習いとしての気づき

私は今、リーダー見習いとして活動しています。
営業マンだった頃は、自分の数字を追うことだけを考えていました。
どうすれば新規を上げられるか。どうやれば目標を超えられるか。
考える対象はいつも“自分”だったんです。
しかし今は違います。
メンバーが成果を出せるように、どんな要素をどう伝えるかを考える毎日。
KPIは一朝一夕では動きません。
施策を打っても成果が出ず、焦りばかりが募ります。
「数字を自分ごとにする」ことに慣れていた私にとって、営業所全体の数字を背負うのは想像以上に重いことでした。
そんな中、上司から問われたんです。
「一番の課題はなんだと思う? その打ち手は? そして、なぜそれが必要だと思う?」
その時の私は、うまく答えられませんでした。
必死に絞り出した言葉には、芯がない。
私は、物事をシンプルに考える力を失っていたんです。
そこから、三つの思考法――ロジカルシンキング・クリティカルシンキング・ラテラルシンキング――を学び直すことにしました。
ロジカルシンキング:筋道を立てて考える
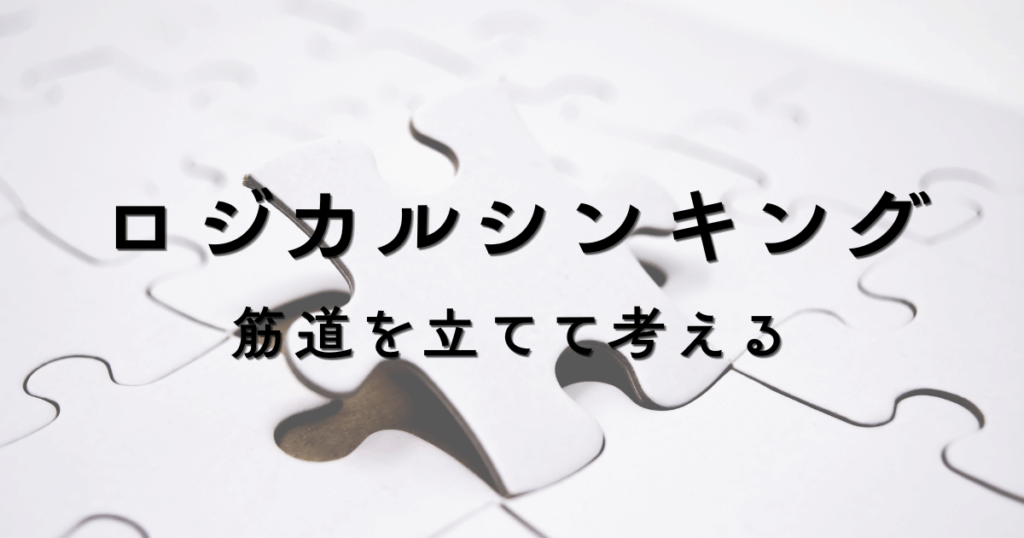
ロジカルシンキングとは、日本語での論理的思考のこと。
物事を要素ごとに分解し、結論・根拠・具体例の順で体系的に整理をして、筋道立てて考えることで矛盾や破綻がないような結論を出すための思考法です。
私の経験
営業効率を上げたいのに成果が出ない時期、上司に「問題を分解してみよう」と言われました。
「営業活動」「顧客管理」「メンバー育成」の3つに分けて洗い出した結果、実は“情報共有の遅さ”がボトルネックだったんです。
それまで「頑張ります」で済ませていた自分が、初めて“根本原因”を言葉にできた瞬間でした。
私の練習方法
そんな成功体験から、私は実生活でもロジカルシンキングを意識して話したりをするようになりました。
私が行った練習を紹介します。
ロジカルに考えるとは、冷たい理屈ではなく迷子にならないための地図を持つことです。
普段の会話から上記3点を意識することで、数ヶ月で劇的に思考能力は改善します。
課題に対する打ち手を考えることに、かなり時間もかかっていた私ですが、練習を進めれば進めるほど、それまで混沌としていた頭の中が整理されて、打ち手の質も飛躍的に向上し、打ち手を出すまでの速度も上昇しました。
クリティカルシンキング:思い込みを壊す勇気
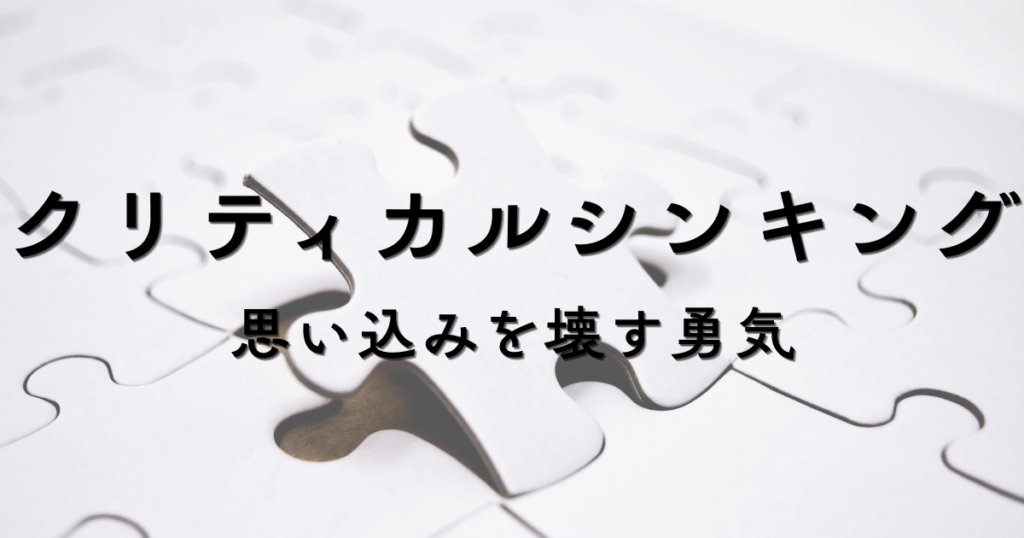
どんなにロジカルに考えても、前提が間違っていれば結果はズレてしまいます。
私は仕事において、この傾向が顕著でした。
だからこそ大事なのが、クリティカルシンキングです。
「本当にそうなのか?」と自分の考えを疑う力を養うことで、仕事だけではなく、日常生活においても物事を考えることがシンプルになり、グッと気持ちが楽になりました。
私の経験
KPIを「商談件数」に設定していた時期がありました。
けれど、数字は順調に伸びていたのに、売上はまったく増えなかったんです。
冷静に見直すと、“数を追えば売れる”という思い込みに縛られていたことに気づきました。
そこで、件数よりも「顧客の質とタイミング」を見直しました。すると、ようやく成果が出始めたんです。
自分の思考を疑うことが、チームを救った瞬間でした。
私の練習方法
クリティカルシンキングは他人を批判する技術ではありません。
自分の思考を点検する習慣です。
思えば、私が学生だった頃に文学批評のゼミで、毎日壁打ちをしていたこの習慣は、このクリティカルシンキングに他なりませんでした。
もう一度、この頃の気持ちと思考習慣を思い出し、ひとつひとつの考えに対して、あらゆる角度から点検をする癖をつけることで、仕事における自身の打ち手設定にも、効果がありました。
ラテラルシンキング:枠を超えて発想する
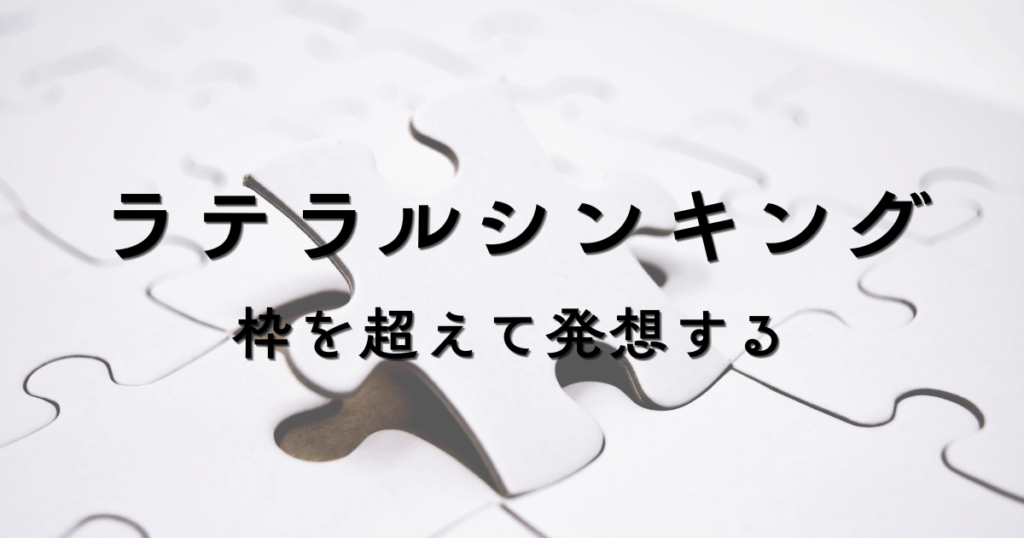
ロジカルやクリティカルが“縦の思考”なら、ラテラルシンキングは“横の思考”です。
日本語に訳すと「水平思考」。
既存の考え方とは異なる角度からアプローチをすることで、イノベーションや革新的なアイディアを生み出す思考法です。
このラテラルシンキングを訓練することで、前提をひっくり返し、違う角度からアイデアを生み出す力となります。
私の経験
営業効率を上げることばかり考えていたある日、「効率化」ではなく「顧客が会いたくなる仕組み」を考えてみたました。
そこで企画したのが“体験型イベント”だったんです。
数字ではなく、関係性を育てる発想に変えたことで、結果的に売上が伸びました。
「前提を壊すこと」が、新しい成果を生んだんです。
私の練習方法
ラテラル思考は、正解を探すのではなく新しい問いを見つける技術です。
私もまだまだ全然考え方は凝り固まっているなと自覚しています。
煮詰まった時には、一度視野を広げてみることにしています。
まとめ:考え続けることが、リーダーの成長をつくる

ロジカルで整理し、クリティカルで検証し、ラテラルで広げる。
この三つの思考法を行き来できるようになると、どんな場面でも“考える力”が折れなくなります。
上司の問いに答えられなかったあの日から、私は少しずつ「考え方」を鍛え続けています。
大事なことは、結論を焦らず問いを立て続けること。
それこそが、リーダーとしての最初の一歩だと今では考えています。
リーダーとしての活動を支えるマインドを哲学や心理学からヒントを探った記事もぜひご覧ください。